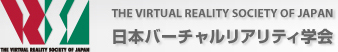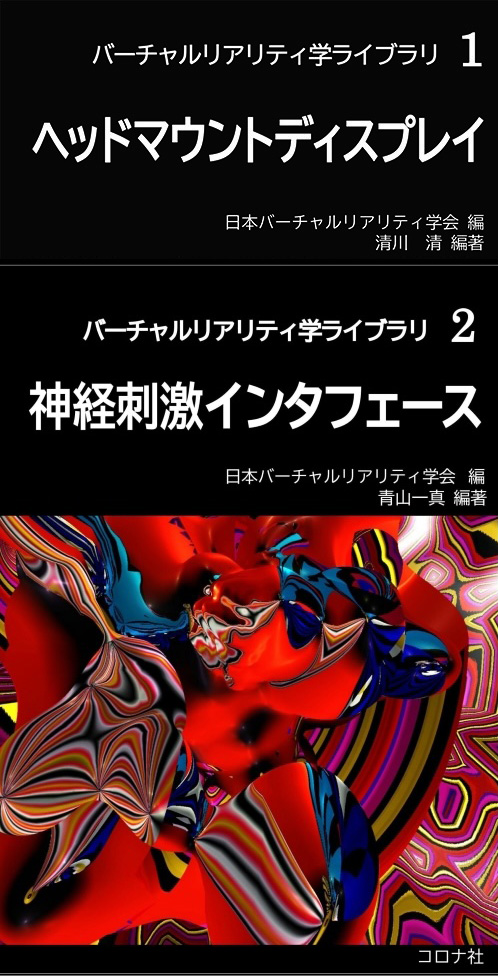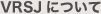特集号のおしらせ
最終更新日: 2025/12/10
今後の特集予定 2
今後の特集予定 3
※一般論文は随時受付しております. →投稿について 過去の特集号については こちら をご覧ください.
【重要】2017年3月末発行のVol.22 No.1より,論文誌は電子発行となりました(J-STAGE).Vol.22 No.1以降に掲載される場合は,論文誌の印刷・別刷りの送付はありませんので,ご了承のうえ投稿ください.電子化前と掲載料に変更はありません.カラー掲載の別途費用は不要となりました.(白黒でもカラーでも掲載料が同額です) 2017年5月29日追記
投稿募集中の特集 1
| テーマ | 【AIとVR】 |
|---|---|
| 締切 | ◆申込締切:2026年2月2日(月) ◆論文締切:2026年2月9日(月) |
| 概要 | バーチャルリアリティ(VR)・拡張現実感(AR)技術は、機械学習・深層学習・大規模言語モデル(LLM)をはじめとするAI技術の飛躍的な進化、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)などの空間コンピューティングデバイスの発展、およびソーシャルVR・メタバースの普及に伴い、かつてない変革期を迎えています。特に生成AI(Generative AI)の実用化は、3D空間構築やアバタ生成のコストを劇的に低減させ、コンテンツ制作の民主化を加速させています。同時に、コンピュータビジョン分野におけるNeRFや3D Gaussian Splattingなどの新たな表現学習技術は、現実空間の高精度なデジタル化を容易にし、実世界と情報世界の境界を融解させつつあります。 こうしたAI技術の進化は、VR/AR研究の多様な側面に影響を及ぼしています。視線・表情・姿勢・生体情報などのマルチモーダルデータをAIがリアルタイムに解析することで、人間の状態や意図を推定し、環境側が適応的に変化するインテリジェントなインタラクションが実現されつつあります。ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)分野では、LLMを搭載した自律型エージェント(AIアバタ)と人間との共存が、VR空間における社会的相互作用や教育・訓練・エンターテインメントの在り方に新たな価値をもたらしています。また、VR環境やデジタルツインは、AIエージェントの学習や評価のための安全で制御可能なテストベッドとしても注目されており、「AI for VR」と「VR for AI」の双方向の関係性が深まっています。 一方で、AIとVRの融合は新たな課題も浮き彫りにしています。生成コンテンツの著作権や真正性の担保、AIエージェントに対する社会的・倫理的受容性、没入環境におけるプライバシー保護、そして人間の認知・行動への長期的な影響など、技術的側面のみならず人文社会科学的な視点を含めた学際的な議論が求められています。これらの技術的・社会的課題に対する多角的なアプローチが、今後のVR/AR×AI研究の発展に不可欠です。 このような背景のもと、本特集号では「AIとVR」をテーマとし、AI技術とVR/AR技術の融合によって切り拓かれる新たな知見、技術、理論、実践を広く募集いたします。基礎的なアルゴリズム開発から応用システム構築、コンテンツ制作手法、認知科学的評価、そして社会実装における課題検討まで、幅広い観点からの投稿を募集いたします。基礎、応用、コンテンツ、総説といった様々な視点での皆様の積極的なご投稿をお待ちしています。なお、使用言語は、日本語、英語、いずれも可能です。 |
| ゲストエディタ |
満上 育久(立命館大学) 平木 剛史(筑波大学) 廣井 裕一(クラスター株式会社) |
| 対象論文・キーワード | 本特集では,AIとVRの融合に関する理論的・実証的研究,各種応用システム開発やコンテンツ製作,システムを構成するコンポーネント等に関する基礎論文,応用論文,コンテンツ論文,総説論文を広く募集いたします.具体的には,下記のような分野を対象としますが,これらに限定されるものではありません.
・VR/ARにおける生成AIを用いたコンテンツ制作(3Dモデル・テクスチャ・モーション・環境生成)とクリエイティブ支援 |
| お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]je.bunken.co.jp) |
今後の特集予定 1
| テーマ | 【ハプティクス特集号】 |
|---|---|
| 締切 | ◆申込締切:2026年5月上旬 ◆論文締切:2026年5月中旬 |
| お問い合わせ | 日本バーチャルリアリティ学会編集事務局(vrsj-edit[at]je.bunken.co.jp) |