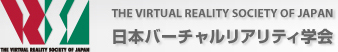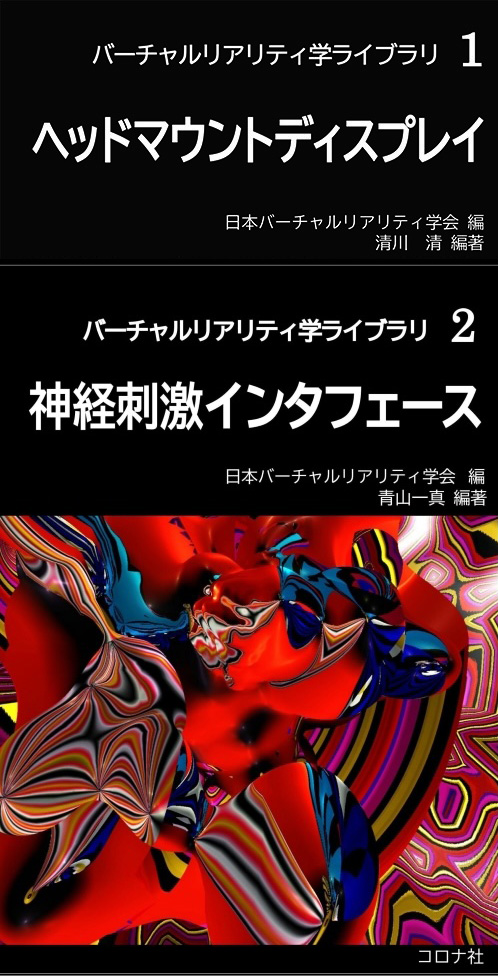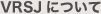エンタテインメントコンピューティング2025
大野元(芝浦工業大学)
エンタテインメントコンピューティング2025(EC2025)は,2025年8月25日から27日にかけて3日間,日本大学文理学部キャンパス(東京都世田谷区)にて開催された.ECは2003年より毎年開催され,今年で23回目の開催となる.
今年のテーマは『EC is borderless』であり,国際会議ICEC2025との連携により,国際性を高めたプログラム編成がなされた.また,全ての口頭発表がデモ・ポスターとしても展示され,発表形態の境界を越えた発表が推進された.さらに,希望者によるEC発表内容をICEC参加者に向けて英語でのデモ発表を行う「インターナショナルセッション」も設けられた.発表は,口頭発表(査読付),口頭発表(レギュラー),デモ・ポスターの3つのカテゴリで募集され,合計で口頭発表35件,デモ・ポスター86件が行われた.会場の広いホールには多数のブースが設置され,ECの特徴である革新的で創造性に富んだ研究を直接体験しながら,活発な議論が繰り広げられていた.2日目の午後には徳井直生氏による「生成AIと創作の未来:音楽領域の実践を通して」と題した基調講演が行われた.
受賞関係では,「漫才カラオケ:未経験者でも漫才を演じることを可能にする漫才実演支援システム」が本会議において複数の賞を獲得した.来場者が誰でもお笑い芸人になったかのように漫才を体験できるこのシステムは,デモ発表において多くの参加者が体験し,会場を盛り上げていた.また,EC独自の「レコメンデモ認定」も例年通り実施され,専門委員によって推薦された魅力的なデモ・ポスター発表が「推し語り」として紹介された.筆者が関心を持った発表のひとつに,「エノコログサを移動体とした振動面上での多様な移動制御」がある.エノコログサの形状を利用し,振動のみで直進や回転といった運動を実現するというユニークな内容であった.
また,今回の発表ではLLMに関する研究が数多く見られた.中でも,ギャル的な言葉遣いを持つAIとの対話を通じて利用者の自己肯定感を高めることを目指した「心理・言語的評価指標“ギャルマイン度”を用いたメンタルをアゲるためのギャルAIとのチャットシステム」は,多くの参加者の関心を引いていた.さらに,「TeachLeague: 自分が育てたエージェントとチームを組んで競う Learning By Teaching 型学習システム」では,AIがあえてわからないふりをし,学習者がAIに知識を教える過程を通じて理解を深める教育支援の新たな可能性を示していた.また,スポンサー企業であるアサヒグループジャパン株式会社と明治大学宮下研究室による共同研究展示は,未来の食のあり方を提示する取り組みとして参加者の注目を集めていた.
閉会式直前には特別企画「大学研究とエンタメ業界は,どう出会う?」が開催され,Cygames Researchの倉林修一氏,サイバーエージェントの高野雅典氏・岩本拓也氏,津田塾大学の栗原一貴氏らが登壇した.大学研究と産業界との接点について活発な議論が交わされ,その中で倉林氏が述べた「論文を提出することは健康診断のようなものであり,技術の信頼性を担保する行為である」という比喩が印象に残った.
今回のEC2025は,全ての口頭発表にデモ展示が伴い,研究を実際に体験しながら議論を深められる点が非常に印象的であった.デモによって口頭発表だけでは伝わりにくい部分まで理解が広がり,発表者と参加者が一体となって楽しみながら新たな可能性を探る姿は,エンタテインメントコンピューティングの新たな可能性を実感でき,今後のさらなる発展を期待させる内容であった.
EC2025の詳細や各賞の結果は公式サイトに掲載されているため,ぜひ参照されたい(https://ec2025.entcomp.org/).なお,次回のEC2026は関西で開催される予定である.